はじめに: 本記事の概要と想定読者
本記事は、注目を集める「半導体」について、わかりやすく解説するシリーズ記事の第一弾です。半導体と言われる物質の特性と注目される理由、そして主要な半導体とその用途について解説をします。筆者は学生の頃から半導体を使った研究をしており、現在は半導体製造プロセスのエンジニアとして活動しています。
半導体材料の製造方法についても解説しているので、ぜひご一読ください!
本記事の想定読者:
- 半導体の性質について知りたい方
- 半導体製品として使われている物質について知りたい方
半導体の基礎:導体・絶縁体との違い
「半導体」の定義を知る前に、「導体」と「絶縁体」の定義を説明します。「導体」は「電気を通す」物質、「絶縁体」は「電気を通さない」物質です。
「半導体」は「特定の条件下で電気を通す」物質です。導体のようにも絶縁体のようにも振る舞うため、「半」導体です。この「特定の条件下で電気を通す」性質のユニークさのため、非常に重宝されてきた歴史があります。
半導体の主な用途
半導体の用途は多岐にわたります。主なものとして、
- CPUやGPUなどの演算素子
- DRAMやSSDを主とする記録素子
- 通信用の高周波半導体
- 太陽電池
- LEDやレーザー、PINを含む受発光素子
- 電圧の変換を行うパワー半導体
- 光触媒
などが挙げられます。用途が多岐にわたるため、Siを中心にそれぞれに適した物質が使われています。
主要な半導体材料とその特徴
シリコン(Si):半導体の王者
Si(シリコン)は半導体の代名詞とも言える物質です。CPUやGPUの演算素子、NANDやSSDの記録素子、太陽電池、高周波半導体、パワー半導体、光通信そしてイメージセンサーなどほとんど全ての用途でSiを使っています。広くSiが利用されている理由は複数あります。
- Siが地球上に大量に存在する
- 大口径で純度が高い単結晶を容易に得られる
- 加工が容易
資源量と生産性が優れているため、非常に低コストに大きく純度の高い単結晶を得られる点が非常な強みになっています。純度の高さは素子化時の歩留まりの高さや不良率の低さに直結します。また、大径のウェハほど素子化時のコストが下がります。現状のSiの単結晶は12インチ(直径約30 cm)に達しています。他の半導体は2~6インチ、一部SiCで8インチであるのに対して、圧倒的に大径で純度の高い結晶を得られています。
GaN(ガリウムナイトライド):高周波とLEDの革新
GaN(ガリウムナイトライド)は日本で初めて製品化された半導体です。1986年に発明され、長年不可能と言われた青色LEDや紫外レーザー向けに生産されてきました。近年は高周波の応答速度に優れるため、通信用の高周波向け半導体に使用されています。また、にわかにパワー半導体としても注目を集めています。
https://eetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/2503/11/news115.html
GaNはSiよりも高周波とパワー半導体としての特性に優れていますが、純度の高い(結晶欠陥の少ない)単結晶を生産する点で困難を抱えており、普及に至っていません。半導体は、基板と言われる結晶の上に、機能を持たせるためのエピ膜を成膜しています。
GaNのエピ膜を得るためには、Siやサファイア基板上に成膜する必要があります。これをヘテロエピタキシャル成長といいます。GaN基板は欠陥が比較的多く存在します。また、成膜後に基板が反るため、大径化が困難という課題も抱えています。現状は6インチでの生産が主流です。
Siの場合は、純度の高い基板の上に、Siのエピ膜を成膜できます。これをホモエピタキシャル成長といいます。このため、非常に純度の高いエピ膜が得られ、反りの問題もありません。
https://pubdata.nikkan.co.jp/uploads/magazine_introduce/pdf_61e4d52d9aa67-4.pdf
SiC(エスアイシー): EVや電鉄等のパワー半導体
SiCはEVの発展に伴い、近年注目を集めていました。トヨタのレクサスやテスラ、新幹線にも実装されています。SiCはSiに比べてパワー半導体特性に優れています。
- バンドギャップがSiより広いため、高温、高電圧に強い(Si: 約1.1 eV、SiC: 約3.3 eV)
- Siより放熱性に優れる(=冷却機構を付けなくて良く、小型化可能。エネルギー消費も小さい)
- 絶縁破壊強度がSiの10倍(=リークしにくい)
また、Siパワー半導体の素子化プロセスを流用出来る点も魅力とされ、注目を集めてきました。SiCの課題もGaN同様、大口径で純度の高い単結晶を生産することが難しい点、そして化学的に安定で硬度が高く脆い性質による難加工性が普及を阻んでいました。しかし、近年は中国を中心とした勢力が積極的に生産を拡大してきたことから生産技術が発展し、8インチまでの大径で純度の高い結晶を得られつつあります。また、難加工性という課題も、レーザースライスという技術や、CMP技術の発展で解消されつつあります。
SiCも日本発の半導体であり、2010年代は日本勢が先行して生産技術を開発してきました。しかし、近年は中国に押されつつあり、EV需要の減速も伴って苦境に立たされています。

GaAs(ガリウムヒ素): 可視及び赤外LED、光センサー
GaAsは可視及び赤外LED用の半導体として広く普及しています。GaAsは一般的にIII-V族(さん-ごぞく)半導体と言われています。InPも同様の枠に含まれています。 GaAsの魅力は、非常に広い波長をカバー出来る発光素子としての機能にあります。
- III-V族半導体はIII族ならGa、Al、In、V族ならAsとPなど複数の元素を選択して、化学組成が異なっても原子間距離等しくしてエピ成長出来る
- ドーパントもSiやTe、MgやCなど複数の選択肢がある
- 結果として、非常に広い波長帯をカバーした純度の高い結晶を得られる
複数の元素の組み合わせで発光波長や電流-電圧特性を得られる点から、Siとの棲み分けができているため、需要は安定しています。一方、レアアースであるGaを使った材料であることから、資源が限られている点に問題があります。GaAs含むIII-V族の技術は成熟期を迎えていますが、今後も車載用センサー(バック駐車時の運転支援や居眠り防止センサー)やLiDARなど需要は旺盛な半導体です。

https://www.material.tohoku.ac.jp/~denko/lecture/denshizairyo/2016/denshi%204.pdf
InP(インジウムリン): 赤外LED、受光素子
InPは主に受光素子(PINおよびAPDダイオード)に使われています。直近では、データセンター向けの需要が旺盛であり、今後は光電融合の分野での活躍が見込まれています。また、エピ成膜によりGaAs以上に長波長の発光が可能なこともあり、肉眼では判断できないイメージングが可能です。
TiO2(酸化チタン): 光触媒の可能性と課題
TiO2は代表的な光触媒です。紫外光を吸収すると強力な酸化作用を発揮し、超親水性という特性を示すため、外壁の防汚剤として粉末が添加されているものもあります。
https://jp.toto.com/products/tile/hydro/
光触媒は半導体が光を吸収して、電子と正孔を生み出す性質を利用し、化学反応を起こす性質を利用しています。最も注目されている分野は水分解による水素製造です。これは、光と水、そして光触媒さえあればエネルギーである水素を生み出せる夢の技術です。
光触媒による水素製造は日本を中心に旺盛に研究が進められています。ボトルネックは
- 太陽光の利用効率の高い半導体の発見
- 表面での反応を促進する助触媒の開発
- 生成した水素と酸素の分離、回収
- 太陽光の利用効率の高い反応システムの開発
などが挙げられます。

Ge(ゲルマニウム): Si以前の演算素子の主流
GeはSiより先んじて実用化された半導体です。はじめトランジスターとして利用され、Siの登場によりその道を譲りました。現在は一部LEDなどで利用されています。
https://www.shmj.or.jp/dev_story/pdf/develop38.pdf
今後が期待される半導体物質
ペロブスカイト型半導体: 次世代の太陽電池
ペロブスカイト型半導体は次世代の太陽電池として注目を集めています。従来のSi型太陽電池と比べて、以下の点で優れています。
- 塗布することで生産出来るため、非常に生産性が高い
- 薄く、軽く出来るため、折り曲げが可能。場所や形状の制約が格段に少ない
いよいよ実用段階が見えてきている技術になります。課題は、環境負荷の低減にあります。Pb(鉛)フリーのペロブスカイト型半導体を見つけることが出来れば加速度的に普及すると考えられます。

ダイヤモンド: 究極のパワー半導体材料
ダイヤモンドも実は有望な半導体材料として注目されています。SiCを超えるバンドギャップ、放熱特性から、ポストSiCのパワー半導体として研究が進められています。しかし、生産性と加工性もSiC以上であり、現状のウェハサイズは2インチがせいぜいです。
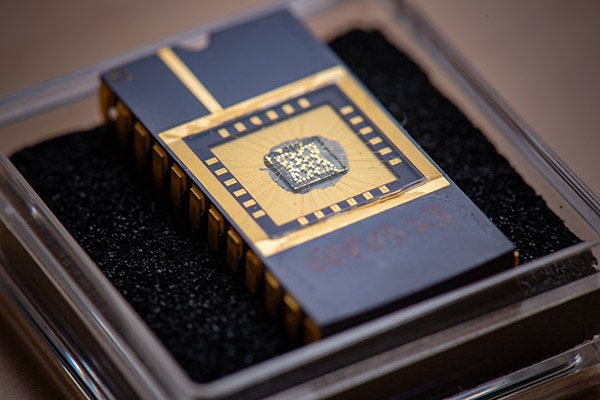
Ga2O3(酸化ガリウム): SiCを超えるパワー半導体
Ga2O3も次世代のパワー半導体材料として注目を集めています。特にβ型と言われる結晶がパワー半導体としての特性に優れており、一部試作されています。こちらも日本発の半導体材料です。
SrTiO3(チタン酸ストロンチウム): クリーン水素製造用の光触媒
水分解による光触媒として、実用化に最も近い材料はSrTiO3が積極的に研究されています。助触媒という水の分解を助ける物質をつけたり、光の利用効率を上げるため、バンドギャップを調整する不純物(ドーパント)を入れることで、比較的に効率よく水の分解が可能な物質です。
光触媒はより優れた材料の探索が進められているため、今後の発展が期待されます。
https://www.shinshu-u.ac.jp/institution/rism/activity/b9450147651570b7eca2ccd625817c32.pdf
まとめ: 半導体の多様性と日本の課題
以上、半導体材料について実用化されているものと今後の発展が期待されているものを紹介しました。「半導体」と一口に言っても、用途に応じて様々に使い分けられており、新たな用途や材料の開発が盛んに行われています。
多くの半導体材料は日本発で作られてきましたが、製品化の遅れや投資不足で中国や米国、欧州に遅れを取ってしまった現状があります。次代の半導体材料は、積極的な投資による製品化が望まれます。
次回予告
今後も半導体に関する素材の特徴や製造プロセスについて解説していきたいと思っています。自戒は半導体前工程の全容を紹介します。ぜひ期待してください!要望あればぜひお願いします!





コメント